
名前を言ってはいけないあのクリスマス

ねぇ、『ギヴァー 記憶を注ぐ者』を読み終えたけど、主人公のジョナスが見た記憶にクリスマスのシーンがあるよね。
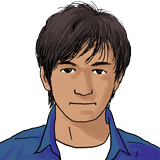
え、そんなシーンあったっけ?
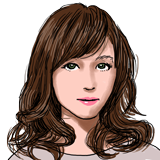
映画ではハッキリ断定されにくい映像にしてあったのよ。小説でも “クリスマス” って文字は一度も出てこないわ。だけど、一般常識的に考えれば、あのシーンはクリスマスね。
ジョーナスは人でいっぱいの部屋にいた。とても暖かく、暖炉では赤々と火が燃えていた。窓をとおして見ると、外は夜で、雪が降っていた。色とりどりの灯がついていた。赤、緑、黄色の灯が、木の上でチカチカまたたいていた。その木というのがふしぎなことに、部屋の中にあるのだ。
(ロイス・ローリー作 『ザ・ギバー 記憶を伝える者』より)

クリスマスツリーやね。言葉でいくつかの色も表現されてるじゃない。
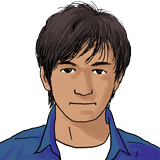
映画ではクリスマスツリー出てきたかなぁ?
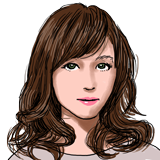
窓からちょっと見えるだけよ。ドアにもリースが飾ってあったでしょ。
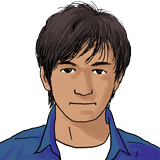
ああ、あれはクリスマスの飾りか。

おばさん、前に言ったじゃない、嘘をつかない人なんていないって。

そら、おらんやろ。とくに子供がいたらね。

サンタさんのことだね。
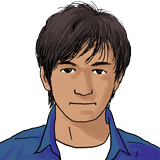
コウノトリが赤ちゃんを運んでくるのもだね。

ついてもいい嘘って、きっとあるよね。
うそつき

うそつきはドロボウの始まりだ! 俺は正直に生きるぜ。なぁブスおばちゃんよwww

なんでも正直が一番なわけないやろ。ドロボーにカギの場所や暗証番号を教える人いる? それに人を傷つけない嘘も、ショックを与えない嘘も、人を楽しませる嘘もあるわよ。

誰か正直な俺を褒めてくれよ!

わたし、ジョナスが “記憶を継ぐ者” に任命された時にもらった新しい規則のところでドキドキしちゃった。
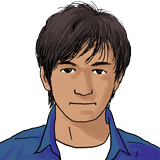
「嘘をついてもよい」て項目?

うん。
ジョナスは、それまで考えもしなかったことに思い至った。この新しい考えは彼をぞっとさせた。もしほかの人たちもーー今の大人たちもーー、〈十二歳〉になった時、自分たちへの指示の中に、同様の恐ろしい一文を見たのだとしたら?
もしすべての人が、「嘘をついてもよい」という指示を受けていたとしたら?
ジョナスの心は揺れた。ぼくはもう、最も無作法な質問をすることを許されているーーしかも必ず答えが返ってくるという。たずねてもいいのだ、考えられるかぎりでは(ほとんど想像を絶することだけれど)。誰か大人に、たとえば父にでもいい、「嘘をつくことがあるの?」と。
しかしジョナスには、返ってきた答えが真実かどうかを知るすべはないのである。
(ロイス・ローリー作 『ギヴァー 記憶を注ぐ者』より)
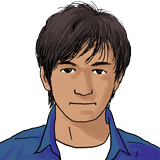
映画ではここまで繊細な表現はされてなかった。この本、読んでみるよ、面白そうだね。
サンタの証明

十二歳にもなれば、サンタが本当にいるかどうかは分かってるわよね。あのクリスマスのシーズンに、世の中みんなで嘘の共犯者になっていることを知るのよ。楽しい雰囲気の中で。

だから『ギヴァー』の物語のコミュニティーではクリスマスがなくなってしまったのかしら?
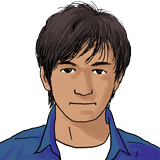
雪がなくなったからじゃないかな? ソリがなきゃトナカイもサンタも来れないし。
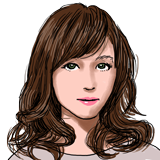
雪がなくてもクリスマスはできるわ。オーストラリアじゃクリスマスは夏なのよ。

サンタがいないなんて誰が証明したんだい?
ぼくは鈴を振ってみた。素敵な音がした。ぼくも妹も、これまで耳にしたこともないような音だった。
でも母さんは「それ、だめじゃない」と言った。
「うん、壊れているんだな」と父さんは言った。
ぼくが鈴を振ったとき、その音は父さんにも母さんにも聞こえなかったのだ。
(クリス・ヴァン・オールズバーグ作 『急行「北極号」』より)

モモが聞いた音楽も、そういう特別なものだったんかしらね?
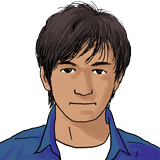
きっと、純粋な人にしか受け取ることができないものがあるんだよ。
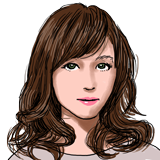
ジョナスも聞こえたわ。
背後の、はるか時空を隔てた彼方、ジョナスが後にしてきた場所からも、音楽が聞こえてきたように思った。だがそれは、ただのこだまだったのかもしれない。
(ロイス・ローリー作 『ギヴァー 記憶を注ぐ者』より)

でも、ただのこだまかもしれないって・・・
聞こえる?

そうそう! 本当は何も聞こえちゃいないんだぜ。『はだかの王様』みてぇによ、ありもしない服を見えると言って着てるふりしてんのと同じでよ、聞こえもしない音を聞いたふりしてるに決まってんだろwww

君にふさわしそうな音楽がありますよ。これはもしかすると、選ばれた人だけが価値のわかる、ばか者には聞こえない音楽かもしれません。

二人ともバカねぇ、こだまは本当の音があるから跳ね返ってくるんやないの!
モモだって、こう言ってたじゃない!
あの音楽はとってもとおくから聞こえてきたけど、でもあたしの心の中のふかいところでひびき合ったもの。
(ミヒャエル・エンデ作 『モモ』より)

そうか! ジョナスは本当に聞いたのね。村人たちが歌うのを。

そして、こだまかもしれない音は、〈記憶を伝える者〉と心の深いところでひびき合ったものかもしれませんね。
「いいようもなくすばらしいものが聞こえるようになり、それが音楽だった。別れる前に、すこしおまえにわけてあげよう」
ジョーナスはきっぱりと首を横にふった。
「だめです。〈記憶を伝える者〉。それは持っていてください。ぼくがいなくなったあとも、あなたのものにしておいてもらいたいんです」
(ロイス・ローリー作 『ザ・ギバー 記憶を伝える者』より)
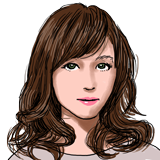
ジョーナスは全てを受け取っても良かったんだけど、〈記憶を伝える者〉に残しておいてあげたかったのよ、きっと。

その優しさが、自分のもとへこだまとなって返ってきた…

モモも最後に唄を歌うわね。それはどんな歌なんかねぇ?
いろんな原因のウソと秘密と遠い歴史の記憶

ねぇ、『ギヴァー 記憶を注ぐ者』に隠された重要な歴史があるみたいに、私たちの現実社会でも過去の歴史に大事なことがあるとしたら、それを知らないと、たどり着けないものがあるのかなぁ?
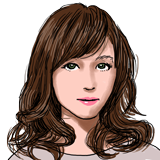
『モモ』には「まえばかり見て、うしろをふりかえらないと…」という章もあるわね。
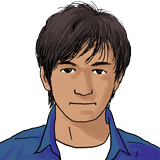
『モモ』でも最初に、何世紀も前に滅んだ文明のことが書かれてるんだよね? だけど、過去の真実を知るのはとても困難な気がするな。

どうして?
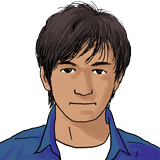
本に書いてあることは全て真実とは限らないよ。ただのおとぎ話もあれば、大ウソの歴史書もあるかもしれない。ウソとほんとうがごちゃ混ぜで、何が何だかわからなくなってしまうものだって、きっとあるよ。
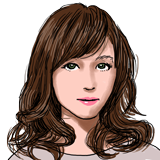
『ギヴァー 記憶を注ぐ者』のジョナスの前任者だったローズマリーの失敗を考えれば、かくしておきたい秘密が生まれるのも分かる気がするわ。人が憂鬱になったり死んだりするんだもの。歴史書ではない生き証人の話だって、嘘がない保証はないわ。

ウソのようで本当のこと、本当のようでウソのこと、悪いウソと秘密、良いウソと秘密・・・・本当のことって、どうしたらわかるのかな?
「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」ジョバンニが云いました。
「僕わからない。」カムパネルラがぼんやり云いました。
(宮沢賢治作 『銀河鉄道の夜』より)
いいかい、そしてこの中に書いてあることは紀元前二千二百年ころにはたいてい本当だ。さがすと証拠もぞくぞくと出ている。けれどもそれが少しどうかなとそう考えだしてごらん、そら、それは次の頁だよ。
紀元前一千年。だいぶ地理も歴史も変ってるだろう。このときにはそうなのだ。
(宮沢賢治作 『銀河鉄道の夜』(旧版)より)
あいてがそれにのってくると、そくざにジジはまくしたてはじめ、ありとあらゆる大うそをならべます。口から出まかせの事件や人物や年代をやたらと聞かされて、かわいそうに観光客たちは頭がこんぐらがってしまいます。中にはそれがでたらめだとわかって、おこって行ってしまう人もありますが、たいていはほんとうの話だと信じこんで、ジジがさいごにぼうしをさし出すと、お金をはらってくれるのです。
(ミヒャエル・エンデ作 『モモ』より)
カシオペイアのことも心配でした。灰色の男たちにつかまったら、どうなるでしょう? 彼女は、カメのことはいっさい口にすべきではなかったと、はげしい自責の念にかられました。
(ミヒャエル・エンデ作 『モモ』より)
また、アミは、ぼくに問題が降りかからないように、次のように言うことを忠告してくれた。
これから語ることのすべてはぼくの単なるファンタジーにすぎず、子どものためのおとぎ話だと。彼の言ったとおりにしよう。
そうこれは、まったくのおとぎ話です。
(エンリケ・バリオス作 『アミ 小さな宇宙人』より)
「これ絶対、墜落しないの?……」
「もし、飛行中に誰かがうそをついたりすると、装置が停止してしまう場合があって……」
「じゃ降ろして! 降ろしてよ! お願いだから」
彼の高笑いで、それが冗談だということがすぐ分かった。
(エンリケ・バリオス作 『アミ 小さな宇宙人』より)
もしすべての人が、「嘘をついてもよい」という指示を受けていたとしたら?
(ロイス・ローリー作 『ギヴァー 記憶を注ぐ者』より)

ねぇ、ミヒャエル・エンデは日本と縁が深いのよね?

自作を翻訳してくれた日本人女性と結婚したそうですよ。

バカなこと言うかもしれないけど、“マイスター・ホラ” のホラって、ホラ吹きのホラだったりしないの?
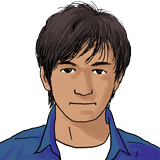
なるほど・・・面白い仮説だね! そういえば、嘘つきのことをなんでホラ吹きっていうんだろう?
ホラ話
【ホラ吹きの言語・由来】
ホラ吹きの「ホラ」は漢字で「法螺」と書き、法螺貝に細工をした吹奏楽器のこと。
「法螺貝」は、山伏が山中での連絡や獣除けに用いたり、軍陣が進退の合図に使用されたもので、見た目以上に大きな音が出る。
そこから、予想外に大儲けをすることを「ほら」と言うようになり、さらに大袈裟なことを言うことを「法螺を吹く」と言い、そのような人を「ほら吹き」と呼ぶようになった。
また、法螺貝は重要な法貝として法会に用いられていた楽器で、仏の説法の盛んな様子も、法螺吹きに喩えられている。

ホラは楽器なんやね。ホラって言葉には「音」が入ってるわけね。
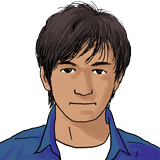
予想外の大儲けも「ほら」なんだね。「お金」とも関係があったんだ。

ほらほら出てきたぜ、宗教の話がよ。仏の説法が盛んなのもほら吹きだとよ。なまねこ、なまねこwww

宮沢賢治の『蜘蛛とナメクジと狸』やないの

ちょっと待ってください。マイスターは賢者に対する尊称で、ホラは時間の単位のことですよ。10章の最後に書いてあります。多分、英語のHourを意味するラテン語のHoraです。

なぁんだ、日本の隠された歴史の糸口でもつかめると思ったのによ。
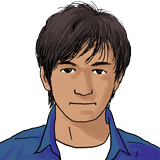
でもミヒャエル・エンデは日本と縁が深いから、もしかしたらこれに気付かせたかったかもしれない!
『モモ』の〈どこにもない家〉を探して

ねえ、”マイスター” って英語やラテン語でどう書くか知らんけど、”ミスター” 的なものじゃなくて ”マイ・スター” だったら「私のお星様」ってことにならない? モモは星空を見上げて、遠いところから送られてくる音楽を聴いてるんだから。
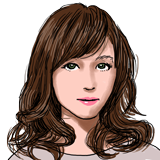
マイスター・ホラがずっと居続けている〈どこにもない家〉って、いったいどこにあるのかしら? 時間はそこからみんなに配られているみたいだけど…。

本当のことって、どこにあるのかなぁ?

「地球のほとんどの伝説の方が、君たちが現実と思い込んで生きている暗い陰気な眠った現実よりも、ずっとリアルなんだよ……」
(エンリケ・バリオス作 『アミ 小さな宇宙人』より)

マイスター・ホラが住んでる〈どこにもない家〉って、どこにあるんだろう?
やみにきらめくおまえの光、
どこからくるのか、わたしは知らない。
ちかいとも見え、とおいとも見える。
おまえの名をわたしは知らない。
たとえおまえがなんであれ、
ひかれ、ひかれ、小さな星よ!(アイルランドの子どもの歌より)
(ミヒャエル・エンデ作 『モモ』の冒頭)

私のお星様は、どこにあるのかなぁ?
「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」ジョバンニが云いました。
「僕わからない。」カムパネルラがぼんやり云いました。
(宮沢賢治作 『銀河鉄道の夜』より)
探しものは何ですか? 見つけにくいものですか?
(井上陽水 『夢の中へ』より)
TO BE CONTINUE
次回の「なぜ児童文学なのか」は・・・
はじめから悪意でウソをつくのは、きっとひとにぎりの人だけ。誰もがただ幸せになりたいだけ。奪い合わず与え合えるのであれば、きっと世界は今よりも良くなっていく。なのになぜか歯車がうまくかみ合わない。ユートピアはどこに?
次回「なぜ児童文学なのか11」は、『アミ 小さな宇宙人』の理想と『ザ・ギバー 記憶を伝える者』の理想がぶつかり合い、『モモ』へと飛び火して思わぬ展開へスピンする(しあわせのためのしわよせ)です。

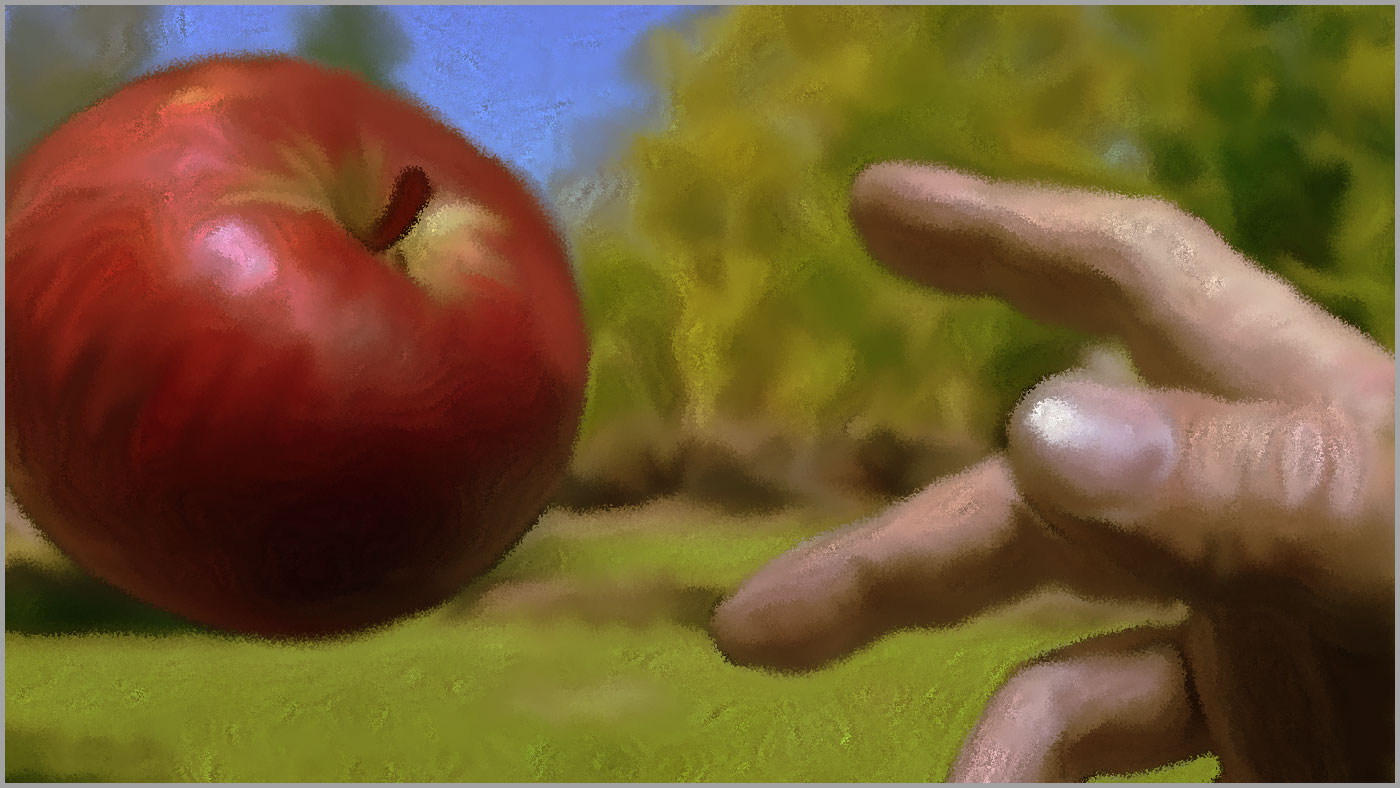


コメント